こんにちは、とし(@tyobory)です。
私は大学編入に携わってから約8年経ちました。ブログでは、大学編入に関する記事を書き貯め、特に経済学部編入に関する記事を中心に書いております。
本記事は、『大学編入って何?』という人から、『編入の勉強に悩んでいる』『独学で経済学部への編入を頑張りたい』といった人向けのまとめ記事となります。
具体的な参考書を教えて欲しいという方は、目次から専門科目対策の項目まで飛んで頂けると幸いです。では、経済学部編入について深掘りしていきます。
【編入】独学で経済学部の編入試験に合格する方法【完全ロードマップ】
大学編入とは何か
まず大学編入とは、2年次または3年次に進級するときに、別の大学に進学する制度です。
編入試験は、一般入試と異なり、国公立大学を複数受験することができます。そのため、実施している大学があれば、その分チャンスがあります。以下、主要な受験校です。
詳しく、「編入とは何か」知りたい方は、下記記事をご参考ください。


大学編入は言わば大学受験のリベンジマッチとなります。
大学編入で予備校に通う必要があるのか
最も受験者数が多いとされる経済学部編入では、予備校に通う人、独学で頑張る人、受験生は様々です。たいてい予備校に説明を聞きに行くと、
編入試験は特殊な試験で、情報が出回ってないから、通わないと中々受からないよ。必ず通ったほうが良い!!(by予備校講師)
と言われます。実際、これは間違いありません。その理由は2つあります。
1.予備校のテキストは過去問から逆算して作られていて、無駄がない
2.編入試験を目指す仲間がいる
編入試験の勉強で一番ありがちなのは、どこまで試験対策したら良いか分からないということです。
予備校の場合、過去問から逆算してテキストが作られており、授業をこなせばOKな部分がある。また、同じように編入を目指す学生が集まるため、目の前にライバルがいる状態かつ常に高いモチベーションで勉強ができます。
そのため、独学よりも挫折する確率は低くなります。マイナーな試験であるがゆえに、予備校に通うだけでも相当なメリットです。
実際、独学でも大学編入に合格できるのか【独学でもチャンスはあり】
私は独学でも十分にチャンスがあると考えています。理由は下記の3でつす。
1.編入予備校に通って合格者の割合は半分
2.英語試験がTOEIC、TOEFLに変更
3.経済数学が導入された(東北大・神戸大)
予備校内部の合格実績データでは、合格率は約55%前後です。残りの半分は、全落ち又はドロップアウトです。全員が全員受かるわけではなく、勉強しない人は普通に落ちてしまうのが現状です。

また、経済学部の編入試験では、外部の英語資格試験を利用するパターンがほとんどです。
TOEIC・TOEFLは学生の能力任せな部分があり、この点で予備校に通う必要はありません。
経済学部編入で最もネックなのは「経済数学」
例えば、中ゼミには「経済数学」の授業は開講されていません。
eccもレギュラー授業があるのが神戸校のみで、現状は夏期講座のWEBスクールの5回だけです。
そのため、今では経済編入って、実は理系出身者がめちゃくちゃ有利な試験になっています。
最上位校の合格を勝ち取るには、独学が必要な要素となっているのが現状です。
大学編入の勉強時間ってどのくらい必要か
私が予備校で働いていたときの感覚ですが、合格する人は朝から晩まで自習室にいたイメージです。
ざっくり、毎日だいたい8時間、総勉強時間は1000時間くらいでしょうか。
編入試験は完全に短期決戦なので、気合入れてガッ!と勉強するのが大事です。
編入試験の勉強時間に関する記事は、以下をご参照ください。

編入試験に本気で取り組んでいる人なら、少なくとも地方国立までは合格できます。
大学編入を成功させるためのマインドアップ
編入試験は周りの学生が遊んでいる環境のなかで、受験勉強をしなければなりません。
そのため、大学編入で合格するには欲望に負けないメンタリティ、そして圧倒的な勉強の積み上げが必要です。

編入試験って我慢比べの試験で、やり続ければどこか必ず合格できる試験です。
なので、淡々と勉強を積み上げられるメンタリティがとても重要となります。
大学編入の志望理由書対策
編入試験では出願時に、志望理由書を書かせられます。正直、特別なものがない限り、志望理由書で差がつくことはないです。
現在、志望理由書を点数化するのは神戸大学くらいで、ほとんど筆記試験で合否が決まります。
とはいえ、大学教授が志望理由書を読むので、読んで苦にならないものを提出したいものです。気を付けるのことは、以下の1点です。
基本的に志望理由書の書き方にはフォーマットがあり、ちゃんと論理構成できていれば及第点です。
志望理由書の関連は下記記事をご参考ください。


独学で経済学部の編入試験に合格するための専門科目対策【マクロ・ミクロ・経営学】
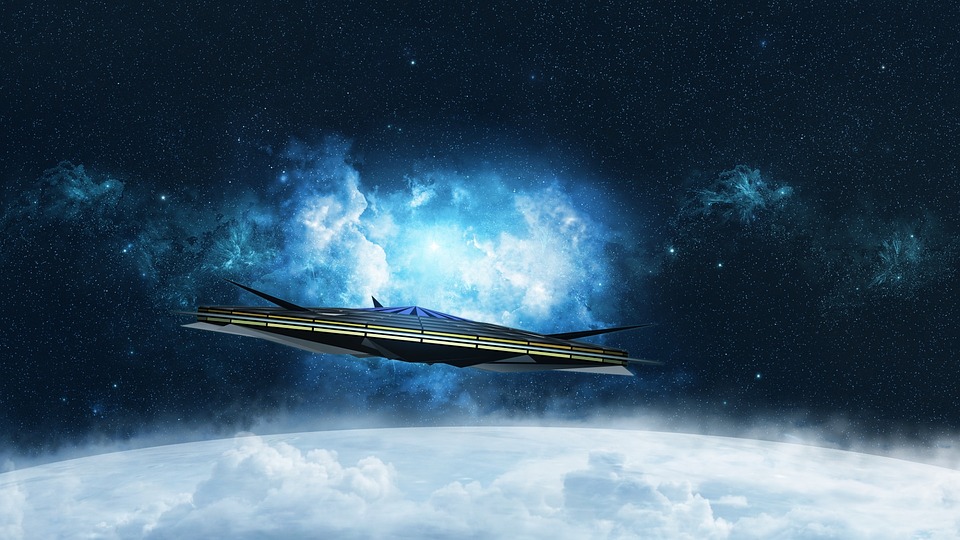
予備校に行かなくても環境は揃っている。
大学編入の小論文対策
近年は、東北大学や神戸大学で小論文の試験がなくなり、経済学部における小論文の重要性は低くなったと思います。
しかし、2年次編入では基本的に小論文が試験科目ですし、一部の地方国公立でも専門科目ではなく、小論文を出すところがあります。
小論文は、200文字ほどの文章のカタマリを3~4つ書いてつなぎ合わせる作業で、800字・1000字・1500字書けないときは、まずは少ない文字数でも書けるようにすることが大事です。
ブログなどの良い記事は構成もしっかりして、論理展開が明確です。文章構成についても、ブログから学ぶことも多く、小論文とかなり相性が良いです。また、ツイッターも140字という制限の中で、自分の伝えたいことを主張する練習としては最高のツールです。
毎日継続して、ブログなら1記事更新すれば2500字くらい書くし、ツイッターを毎日15ツイートすればば、2100字の分量になります。
小論文で一番大事なのはアウトプットなので、スマホを触ってる時に、ちょっとした文章を書いてみるのもありです。以下、小論文とブログについての記事です。ぜひご覧ください。

過去問収集こそ、編入受験生がやるべき最重要事項
編入試験の中で、何が最も重要かと言えば、間違いなく過去問を回すことです。
理由は3つあります。
1.各大学ごとに問題の傾向がある
2.大学間で問題を使いまわしている
3.過去問による傾向対策から、大学ごとに使うべき参考書が変わる
例えば、旧帝でも、名古屋大と神戸大とでは、出題範囲も出題内容も全く異なります。
ただし、旧帝大学や上位の難関大学の過去問を10年ずつやると分かりますが、数値が違うだけで大体は使いまわしです(2019年京大の試験は、過去出題されたものをほぼ一緒でした)。
もちろん、大学ごとに傾向は少し違うので、使うべき参考書が若干変わったりもします(京大なら齋藤誠先生の「マクロ経済学」、大阪大学なら安田先生の「経済学で出る数学」、神戸大なら芦谷ミクロなど、関連した教授の専門書を使うのがセオリーです)。
ここで、過去問については、みさき@編入ライブラリーさんが、横浜国立大・東北・神戸(経済)・名古屋 小樽商科大学の過去問について、noteで公開してくれていますので、是非過去問を確認してみてください。

以下では、さらに経済学編入の試験対策に関する記事を紹介しております。
経済学部編入の試験対策【マクロ経済学・ミクロ経済学・経営学・経済数学】
経済・経営系の編入試験では、専門科目としてマクロ経済学・ミクロ経済学・経営学・経済数学が出題されます。下記は、マクロ経済学とミクロ経済学の出題範囲と内容をまとめた記事となります。


また、本ブログ内に、
というカテゴリーで、ブログ記事が作成されております(TOPに掲載してあります)。
こちらは、上記のマクロ・ミクロの出題範囲を上から順に記事を作成しており、編入で学んだものをベースに、ブログ記事として書き起こしています。
演習問題等はありませんが、予備校に通っている人はこんなことを学んでるんだ!っと思って参考にしていただけると幸いです。
この他に、経済学部編入で使える専門書・参考書を下記の記事で紹介しています。
【大学編入】経済学部編入で使える参考書 ①【マクロ経済学】
【大学編入】経済学部編入で使える参考書 ②【ミクロ経済学】
【大学編入】経済学部編入で使える参考書 ③【経営学】
【大学編入】経済学部編入で使える参考書 ④【経済数学】
【大学編入】経済学部編入で使える参考書 ⑤【会計学】
個人的な意見ですが、マクロ・ミクロの計算問題について、公務員用のテキストはそこまでおすすめしておりません。
理由は2つです。
例えば、「スーパー過去問ゼミ」などの公務員用テキストには、効率的に値を出す公式が載っています。
これは、あくまで公務員の問題を解くため用で、編入試験では公式がつかえないことなんてざらにあります。また、途中の計算式も省くので、良いことはほとんどありません。
小手先だけのテクニックだけでは解けない問題の方が、圧倒的に多いです。
(大学レべル的には、旧帝大・横国・筑波など)
ですから、上位大学を目指すならば、過去問をベースに、専門書を丁寧に読むことをおすすめします。
アンコウ氏による過去問をベースとした経済学問題集【マクロ・ミクロ】
Twitterの編入界隈には、経済学部に編入合格された方が数多くいらっしゃいます。
その中で、精力的に活動されている有志の一人がアンコウさんです。
アンコウさんは、編入の過去問をベースに経済学問題集を作成し、なんとnoteで問題集が発売されています。
私自身もこういった書籍を書こうとしましたが、断念しました(笑)
—一番最初にコンテンツを作った人がエライ!—
私はnoteの方を購入させて頂きましたが、お世辞抜きでほぼ文句なしの出来かなと。
(情報商材らしく、何か胡散臭さあるかもしれませんが(笑))
一通り確認した限りでは、編入で出題されるマクロ・ミクロの問題はほとんど押さえられていて、かつ過去問ベースであるため、買わない理由が見当たりません。
演習問題もすべて解説がついているので、問題集パック(もしくはマクロ経済学とミクロ経済学のnote)はオススメです。
→これで本当に予備校いらずで対策ができます。

本当にすべて過去問ベースで作成されていて、「アンコウさんすげえ」って思っちゃいました。
過去問の整理から始まり、解答・解説を作るのも、途方もない作業量・作業時間かかるので、半端ないです!
編入合格された方々が情報発信してくれるようになり、この1~2年で経済学編入の界隈はかなりの情報で潤ってきましたので、色んな有志の方に感謝です!
以下、SNS上のサークルや経済塾について、サクッとご紹介します。
SNS上の編入サークル・経済塾について(予備校以外)
さらに、twitter上では、#編入サークル というタグで、編入対策がオンラインサロンで活発的に行われています。
私自身、全く関わっておりませんが、今年度はおそらく「経済・経営編入試験対策サークル」が経済・経営学系の合格者の最大派閥になると思います。
→運営者は、新撰組@大学編入
R3年の合格者実績(経済学部)
京都大学—1名、大阪大学—2名、神戸大学(経営)―4名、神戸大学(経済)―1名、名古屋大学—5名、九州大学—1名、横浜国立大学—4名、埼玉大学—2名、法政大学(経営)—2名、筑波大学—1名
こういったオンラインサロンが拡大していくのは必然ですよね!
月額2,980円で年間で約36,000円ほどですが、アドバイザーは基本的に旧帝大・上位国立大の合格者で構成されています。Slackでの運営で、編入仲間も作りやすく、かなりおすすめです。
個人的には、月3000円程度で学習管理等してもらえるなら、相当安いと思います。
また、私は大学院進学のとき「経済塾EMS」という所で勉強しました。

週1日(月4万円)で、私は週2日通っていたため、月謝で月8万円ほど支払っていました。
東大や一橋大大学院の経研に進学する人はEMS出身の人もかなり多いです。
東京にいる人で、上位旧帝大の受験、試験科目はミクロ経済学・マクロ経済学のみ、大学院進学まで考えている人なら、編入受験生でもおすすめです。
人生の中で、経済学の学力が一番伸びたのは「経済塾EMS」にいたときです。市販の参考書を使って勉強してましたが、レベルが高すぎて、塾以外の日でも朝から晩まで経済学の勉強をしてました。
以上、他の選択肢も色々あったりします、そして迷ったら#編入サークル が、経済学部編入の中で今のところ一番コスパが良いかなと考えています。
終わりに:やるからには最後まであきらめない
編入試験はやれば受かる試験です。一般入試では入れない大学に合格できる可能性も秘めています。
あとは、この試験に自分自身がどのような価値を見出し、受験勉強に取り組むのかによります。
やると決めたら、ひたむきに勉強すれば、必ず合格できる試験です。
このブログを通じて、経済学部への編入を受験される方を応援できたら幸いです。

是非、他の記事も参考にしてくださいね!ではでは







コメント