こんにちは、とし(@tyobory)です。
ブログ記事更新45日目となります。
経済系の編入試験では、試験科目で「マクロ経済学」と「ミクロ経済学」が出題されます。
大丈夫です。この記事をはじめ、編入試験で出題される内容について、ブログを通じて公開していきます。
本記事では「マクロ経済学」について掘り下げていきます。
マクロ経済学(編入試験対策)
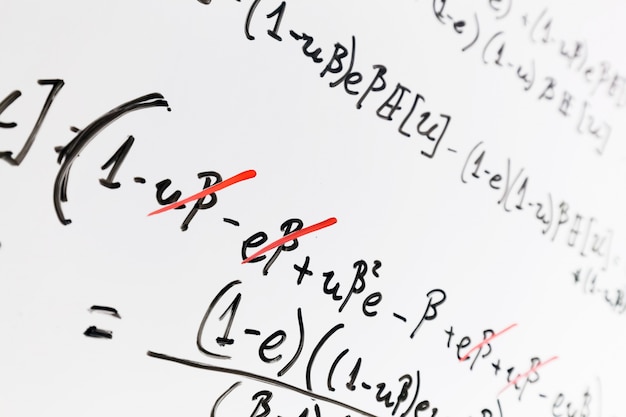
マクロ経済学の基礎を押さえる。
国民経済計算
マクロ経済学の基本です。
国民所得の概念を理解し、国民所得の決定理論について習得しましょう。$\\$
国民所得
- 三面等価の原則(国内総生産・国民総所得・国民総支出)
$\small GDP=GDI=GDE$( $\small P:Product I:Income E:Expenditure$ )
- $\small NDP・NNP・NI$(国内純生産・国民純生産・国民所得)
価格指数(物価指数)
- 名目・実質の違いを理解
- パーシェ価格指数($\small GDP$ デフレーター)
- ラスパイレス価格指数
45度線分析( GDP(国民所得)の決定理論)
- $\small Y =C+I$(基本)
$\small Y_d=C+I+G$(政府支出あり)
$\small Y_d=C+I+G+EX-IM$(海外貿易含む)
- ケインズ型消費関数( $\small C=c_0+c_1Y$ )
- 基礎消費・限界消費性向・平均消費性向【 マクロ経済学-02 】
- 貯蓄関数・限界貯蓄性向【 マクロ経済学-03 】
- $\small S=I$
- 有効需要の原理
- $\small S-I+T-G=EX-IM$
- 非自発失業・完全雇用・完全雇用国民所得
- デフレ・ギャップ
- インフレ・ギャップ
- 乗数効果
- ビルト・イン・スタビライザー

【マクロ経済学】消費関数とは何か【限界消費性向と平均消費性向を理解】
こんにちは、とし(@tyobory)です。
マクロ経済学第2回テーマは「消費関数」についてです。
マクロ経済学でもミクロ経済学でも、所得と消費の関係について、それぞれ理論モデルがあります。マクロ経...

【マクロ経済学】貯蓄関数とは何か【限界貯蓄性向と平均貯蓄性向】
こんにちは、とし(@tyobory)です。
マクロ経済学第3回テーマは「貯蓄関数」についてです。
今回の目次:「貯蓄関数」
1.貯蓄関数(Savings function)
2.限界貯蓄性向(...

【マクロ経済学】乗数効果とは何か?【政府支出乗数・租税乗数・均衡予算乗数】
本記事では、政府支出や租税、投資などの変数を定義し、乗数効果を解説しています。マクロ経済学の目的は国民所得(GDP)を増加させることであり、どのような要因が国民所得に影響を与えているのかを考察します。

【マクロ経済学】インフレ・ギャップとデフレ・ギャップ【完全雇用国民所得】
本記事では、財市場の均衡から、インフレ・ギャップとデフレ・ギャップについてまとめています。労働市場において完全雇用が達成された場合の完全雇用国民所得を用いて、それぞれの不均衡を説明し、財政政策(総需要管理政策)による調整を取り上げています。
IS-LM曲線
編入試験で頻出の分野です。
計算問題から論述問題まで対応できるようにしときましょう。$\\$
IS曲線
- 投資関数
- $\small IS$ 曲線の導出
- $\small IS$ 曲線シフト
- 超過需要・超過供給

【マクロ経済学】IS曲線の求め方・導出について【IS曲線と財政政策】
IS曲線は財市場における利子率と国民所得の関係を表した曲線である。IS曲線の特徴は、投資と貯蓄が均衡し、国民所得は利子率の減少関数となっている。IS曲線は、投資曲線、45度線、貯蓄曲線から導出される。また、IS曲線は財政政策を発動すると右にシフトする。
LM曲線
- 貨幣市場・貨幣の機能
- 取引動機・予備的動機・投機的動機
- 債券価格(コンソル債)
- 流動性のわな
- マネーサプライ・名目(実質)貨幣供給・ハイパワード・マネー
- [現金・預金比率]・[準備金・預金比率]・貨幣乗数・信用創造
- 流動性選好仮説
- $\small LM$ 曲線の導出
- $\small LM$ 曲線のシフト
- 超過需要・超過供給

【マクロ経済学】貨幣需要とは何か?【流動性選好仮説と流動性の罠】
本記事では、貨幣市場の貨幣需要をテーマにまとめています。ケインズ派は、貨幣需要において「流動性選好仮説」という利子率と債券価格の関係性から、貨幣需要について定義し、不況時には「流動性の罠」が発生することを主張しています。

【マクロ経済学】貨幣供給とは何か?【マネーストックとハイパワードマネーを理解】
貨幣供給量はマネーストックにより決定されます。特に、マネーストックの総量を決める金融政策の手段は主に3つあり、①公定歩合操作、②公開市場操作、③法定準備率操作の3つである。以上をもとにして、貨幣市場の均衡についてまとめています。

【マクロ経済学】LM曲線の求め方・導出について【LM曲線と金融政策】
LM曲線は貨幣市場における利子率と国民所得の関係を表した曲線である。LM曲線の特徴は、貨幣需要と貨幣供給が均衡し、国民所得は利子率の増加関数となっている。LM曲線は、資産需要曲線、45度線、取引需要曲線から導出され、金融政策が発動されると右にシフトする。
IS-LM曲線の同時分析
- 均衡利子率・均衡国民所得
- 財政政策の効果
- クラウディングアウト
- (財源)増税の政策・市中引受の国債・日銀引受の国債
- 金融政策(金利政策・公開市場操作・法定準備率操作)の効果
- IS曲線の形状・投資の利子弾力性
- LM曲線の形状・貨幣需要の利子弾力性
- ストック市場(資産市場)ワルラスの法則

【マクロ経済学】IS-LMモデル分析①:財政政策・金融政策【クラウディング・アウト】
本記事では、IS-LMモデルにおける財政政策と金融政策の効果について考察しています。IS-LMモデルでは、財市場と貨幣市場の同時均衡を想定し、拡張的な財政政策を発動すると、クラウディングアウトが発生するため、併せて解説しています。

【マクロ経済学】IS-LMモデル分析②【利子弾力性と政策効果の大小】
マクロ経済学のIS-LMモデル分析において、財政政策と金融政策が無効となる場合があります。これはIS曲線とLM曲線の利子弾力性の大小により政策効果が変化し、国民所得の変化に影響を与えます。本記事では、財政金融政策がどのような場合に無効になるのか考察していきます。

【マクロ経済学】IS-LMモデル分析③【公債の市中消化・中央銀行引受】
本記事では、IS-LMモデルを拡張し、公債の市中消化・中央銀行引受による財政政策の効果についてまとめています。また、公債負担論としてリカードバローの中立命題を取り上げ、諸議論の流れを整理しています。
マクロ経済学(応用単元)
AD-AS曲線
$\small IS-LM$ 曲線をベースに、$\small AD-AS$ 曲線が導出されます。
AD曲線
- $\small AD$ 曲線の導出
- $\small AD$ シフト(形状)

【マクロ経済学】AD曲線(総需要曲線)とは?【求め方/導出方法】
AD曲線は、Aggregate Demand Curveの略で、総需要曲線と呼ばれます。このAD曲線は、IS-LMモデルから求められます。本記事では、AD曲線をIS-LMモデルから導出し、総需要管理政策によるAD曲線のシフトについてまとめています。
AS曲線
- 労働需要・労働供給
- 名目賃金・実質賃金
- 古典派とケインズ派の違いを理解
- 古典派の第一公準(実質賃金($\frac{w}{p}$)=労働力における限界生産力($\small MP_n$) )

【マクロ経済学】古典派とケインズ派の貨幣数量説【貨幣の中立性】
マクロ経済学は、歴史的にみて古典派経済学とケインズ経済学の対立があります。古典派の貨幣数量説では、貨幣は実物経済に影響を与えないことを展開し貨幣の中立性を、対するケインズは貨幣の非中立性を主張し、金融緩和政策の有効性を展開しています。本記事では、両者の貨幣数量説をまとめています。
- $\small AS$ 曲線の導出
- $\small AS$ 曲線のシフト(形状)

【マクロ経済学】AS曲線(総供給曲線)とは?【求め方/導出方法】
AS曲線は、Aggregate Supply Curveの略で、総供給曲線と呼ばれます。AS曲線は労働需要曲線と労働供給曲線から導出されるが、古典派とケインズ派で解釈が異なります。本記事では、AS曲線を古典派とケインズ派に分けて解説していきます。
AD-AS曲線の同時分析
- 均衡物価水準・均衡国民所得
- ディマンド・プル・インフレ
- コスト・プッシュ・インフレ
- ハイパーインフレ
- スタグフレーション

【マクロ経済学】AD-ASモデル分析【総需要管理政策とインフレ】
本記事ではAD-ASモデル分析を解説しています。AD-ASモデルは物価水準と国民所得の関係性を表したモデルであり、インフレと密接に関係しています。ここでは、インフレについてディマンドプルインフレとコストプッシュインフレについて考察します。
国際マクロ経済
国際収支(国際経済)
- 国際収支・経常収支・資本収支
- アブソープション・アプローチ
- $\small IS$ バランス・アプローチ

【マクロ経済学】国際収支(BP)・経常収支・金融収支(資本収支)とは?
本記事では、開放経済モデルの基礎となる国際収支・経常収支・金融収支(資本収支)についてまとめています。国際収支は、経常収支、資本移転等収支、金融収支(資本収支)、誤差漏洩の4項目で構成されており、この記事では経常収支の観点から、資本の動きについて確認しています。
為替レート決定論(国際経済)
- 外国為替・外国為替市場・為替レート
- 変動相場制・固定相場制
- 国際収支説・$\small J$ カーブ効果・マーシャル=ラーナーの条件
- 購買力平価説・一物一価の法則
- アセット・アプローチ
$\\$
マンデル=フレミング・モデル(国際経済)
- 国際収支( $\small BP$ )=経常収支( $\small CA$ )+資本収支( $\small CF$ )
- $\small BP$ 曲線の形状(資本移動なし・完全・不完全)とシフト
- 資本移動完全:固定・変動相場制時の財政政策・金融政策の効果
- 資本移動なし:固定・変動相場制時の財政政策・金融政策の効果
⇒「資本移動なし」はほとんどでないイメージ。3が重要

【完全資本移動】マンデル=フレミングモデルと為替相場【固定相場制・変動相場制】
本記事では、完全資本移動におけるマンデル=フレミングモデルの財政・金融政策の効果を考察しています。マンデル=フレミングモデルでは、固定相場制と変動相場制によって、財政政策と金融政策の効果が異なるため、その政策的効果の違いについてまとめています。

https://wanna-be-work-mundell-fleming-model-02
古典派経済学
- 古典派の二分法(貨幣の中立性)/貨幣ヴェール観
- 貨幣数量説
- フィッシャーの交換方程式
- ケンブリッジの数量方程式
- マーシャルの $k$

【マクロ経済学】古典派とケインズ派の貨幣数量説【貨幣の中立性】
マクロ経済学は、歴史的にみて古典派経済学とケインズ経済学の対立があります。古典派の貨幣数量説では、貨幣は実物経済に影響を与えないことを展開し貨幣の中立性を、対するケインズは貨幣の非中立性を主張し、金融緩和政策の有効性を展開しています。本記事では、両者の貨幣数量説をまとめています。
マネタリスト
- フィリップス曲線・オークンの法則
- 自然失業率仮説(自然失業率・期待インフレ率)
- 短期フィリップス曲線
- 長期フィリップス曲( $\small k %$ ルール)
$\\$
合理的形成学派
- 静学的期待
- 合理的期待
- ルーカス批判
- リカード=バローの中立命題
$\\$
消費関数の理論
- ケインズ型消費関数(短期)
- クズネッツ型消費関数(長期)
- 恒常所得仮説
- ライフ・サイクル仮説
$\\$
投資関数の理論
- ケインズの投資理論
- トービンの $\small q$
$\\$
経済成長理論
リアル・ビジネス・サイクルの理論
- 名目(実質)利子率
- 期待インフレ率
- フィッシャー方程式
- 技術革新
- 労働供給の異時点間の代替
$\\$
成長会計
- 成長会計
- ソロー残差( $\small TFP:Total Factor Productivity$(全要素生産性) )
$\\$
ソロー=スワン・モデル
- 資本ストック成長率
- 労働人口成長率
- 労働一人あたり資本( $\small k$ )
- ソロー=スワン・モデル
- 定常状態
- 消費の黄金律
この経済成長理論は、これまで上から習ってきたことの応用です。
基礎ができていないと、内容がチンプンカンプンになります。
これが「マクロ経済学」の試験で出る出題範囲です
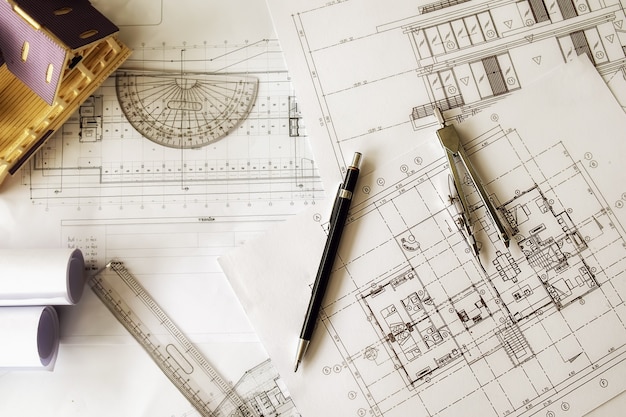
大事なのは、理論を覚えること。
マクロ経済学の勉強方法
マクロ経済学は、ミクロ経済学と比べて、計算量は少ないです。$\\$
そして、すべての土台はIS-LM曲線です。$\\$
ここをマスターしないと、AD-AS曲線、マンデル=フレミング・モデル、経済成長理論もすべて解くことができません。$\\$
なので、必ずIS-LM曲線はマスターしてください。$\\$
勉強の手順として、この記事に掲げた項目を上から順々につぶしていくだけです。$\\$
これで、予備校生が学ぶ内容+αのことを押さえられます。$\\$
マクロ経済学のオススメ参考書は、以下の記事に載っていますので、合わせてご参考ください。

【大学編入】経済学部への編入で使える参考書①【マクロ経済学編】
経済学部の大学編入では、専門科目として「ミクロ経済学」「マクロ経済学」が出題されます。本記事では、経済学部編入で使えるマクロ経済学の参考書をまとめております。
終わりに:計算よりも理論が大事
マクロの計算は公式があり、それに当てはめて計算していくだけなので、そこまで難しい問題はありません。
しかし、財政・金融政策がGDPにどのくらい影響があるかなど、理論を正しく知っていないと、何の計算をしているかイメージできないということがあります。
逆に理論を知っていれば、計算で使う変数やグラフがわかるので、まず最初に理論から学んでいってください。

ゴリウサギ
極論をいえば、マクロは暗記科目なので、ゴリゴリ暗記していけばOK

とし
ってな感じで、一つ一つ、コツコツと勉強を積み重ねていきましょう!
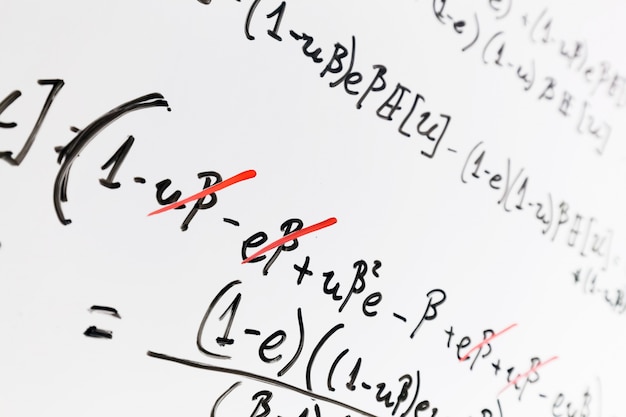


















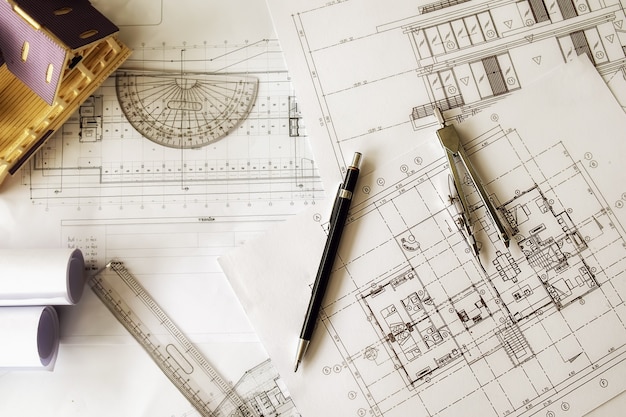








コメント